家族信託の受託者を法人にできる?メリット・デメリットや向いているケース
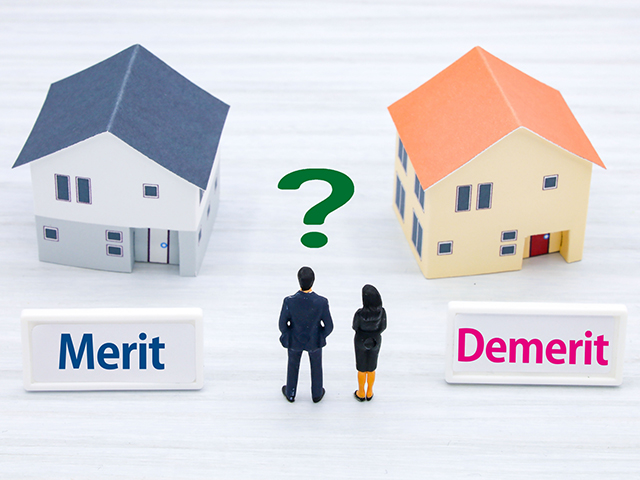
この記事の目次
家族信託で受託者を個人にお願いする場合は信託財産を管理・運用する能力があるかどうかが重要です。
民間の信託会社の民事信託を利用する場合は、金融機関が受託者となりますので安定感を魅力に感じる方が多いでしょう。
今回は、家族信託を活用する場合の受託者を法人にできるかと、そのメリット・デメリットや法人にした方が良いケースなどについて確認していきます。
家族信託は法人を受託者にできる
家族信託の「受託者」は個人(自然人)だけでなく法人も務めることが可能です。
家族信託は遺言や成年後見制度ではできないことも可能になり、不動産賃貸業など収益を産みだす資産活用を含めた財産の承継に有効です。
親族が運営する法人を活用することもできますが、財産管理を主たる目的とする新たな法人を設立することも可能です。
法人を受託者とすることの最大のメリットは、個人とは異なり病気や死亡のリスクがなく、信託財産の長期的運用が可能となることです。
受託者となる法人の種類
受託者として契約可能となる法人の種類には家族や親族が設立した法人で株式会社や合同会社なども可能ですが、一般の法人が営利目的で信託を引き受ける場合には、信託業法に基づく登録等が必要になりますので注意が必要です。
信託業を行う法人としての登録や許可には、資本金の要件や経営基盤の安定性など要件が厳しく容易ではありません。
家族信託では「財産管理」が主な目的である場合が多いので、法人の形態としては非営利活動ができる「一般社団法人」が適していると言えます。
一般社団法人をすすめる理由
一般法人は営利を目的としていますので信託業許可を取得する必要がありそのハードルの高さは前述のとおりです。
そのため、家族信託の受託法人については、財産管理を主たる目的とする「一般社団法人」を設立することがお勧めで、財産の長期的な管理・運用をその目的に沿って組織的に行います。
法人を家族信託の受託者にするメリット
財産管理を目的とした家族信託を活用し、法人を受託者とするメリットについて見ていきましょう。
単純に、個人負担で請け負っていた費用(例えばインターネット費用などの実費)を法人の経費にすることができる点なども魅力です。
その他にも、事業に必要な経費の計上や旅費・交通費の精算なども可能になります。
家族信託の制度そのもののメリット・デメリットについては、こちらをご確認ください。
受託者の変更手続きを簡素化できる
家族信託で信託財産を決め受託者に託す際には、財産の内容によっては多くの変更手続きが必要になります。
例えば、信託財産に不動産が含まれる場合には、不動産の所有権移転登記にはじまり、火災保険の名義変更まで多くの手続きが発生します。
また、賃貸収益を生み出すような不動産の活用や事業承継の場合は世代を超えた長期的な運用を見越して家族信託を活用しますので、受託者が「個人」である場合には、受託者の病気や死亡など予期せぬ事態に都度対応する必要性を考えておく必要があります。
つまりこのような財産の承継を目的とする場合の受託者には「法人」が適していると言えるでしょう。
法人を受託者としておけば、信託財産の変更手続きは、基本的には初回のみで運用可能となり、手続の簡略化につながります。
家族信託の予期せぬ終了を避けられる
家族信託の受託者が「個人」である場合は、病気や予期せぬ死亡などにより受託者が不在状態に陥るリスクがあります。
そして受託者不在の状態が1年間継続したときには信託法大163条2に該当し、いわゆる「1年ルール」により、信託は強制的に終了することになります。
家族信託の「1年ルール」の要件は下記になります。
- 受託者が受益権の全てを持っている状態(受託者=受益者)が1年間継続したとき
- 受託者がかけた状態が1年間継続したとき
このような予期せぬ理由により家族信託の強制終了を避けるためには、受託者を「法人」にすることです。
少人数であっても組織的な運営を行うことができ、財産管理の安定性や継続性が期待できます。
家族信託の「1年ルール」の詳細についてはこちらをご確認ください。
家族で意思決定できる
受託者を法人にした場合は、組織運営として財産管理を行いますので、個々の家族のメンバーが直接受益者となった場合に起こり得る利益相反やトラブルを回避することが可能となります。
例えば、複数の子供をメンバーとする法人を受託者にすることで、家族のメンバーが信託に関する意思決定に参加することができるようになることが大きなメリットと言えるでしょう。
特に複数の相続人がいる場合は公平性を保つためにも役立ちます。
法人を家族信託の受託者にするデメリット
これまで家族信託の受託者を法人化した場合のメリットを見てきましたが、収益の多寡に関わらず、法人の維持には一定のコストや手間がかかることは想定しておくべき点と言えるでしょう。
法人化には設立費用にはじまり、役員報酬や法人税、会計報酬なども発生します。
また法人は収益が赤字であっても法人住民税も発生しますので、維持コストを支払うための収益が見込めるかを十分に検討する必要があります。
家族信託で法人を受託者にした場合の費用
一般社団法人を設立する場合には下記のような費用が発生します。
また、これらにかかる費用は信託財産から支払うことが一般的です。
【設立時にかかる費用】
- 登録免許税:約6万円
- 定款認証手数料:5万2000円
【法人の維持費用】
法人は赤字経営でも法人住民税が発生し、法人住民税の均等割として年間7万円の税金がかかります。
そのほかにも、税務申告を行う際の税理士報酬や、役員変更登記には別途費用が生じます
法人への信託報酬にも注意
受託法人の信託報酬についても確認しておきましょう。
信託法上、信託報酬には制限がありませんので任意に設定可能ですが、事業収入に対して報酬金額が高すぎると「贈与」とみなされ、贈与税が課税される場合があります。
また高額な報酬は「みなし贈与」なる可能性もあるため、事業収入の10%までにとめておくことが妥当と言えます。
つまり、法人設立により発生する月または年間のランニングコストを把握し、信託財産から生み出される収益の10%程度を法人の信託報酬とすることが可能であれば法人化が適していると判断する一つの材料になります。
家族信託の受託者の法人化が向いているケース
これまでの解説をもとに、受託者の法人化が適しているケース、個人の受託者に適しているケースなど確認していきましょう。
【法人の受託者が向くケース】
- 不動産賃貸業など家賃収入がある不動産を多く所有している場合
- 受託者が高齢
これらのケースでは、家族複数のメンバーで受託法人を組織して透明性の高い財産管理を行い、家族の全員での意思決定を行うことが可能になります。
また、高齢の受託者が含まれていても、受託者不在などのリスクを回避し、永続的な持参管理の実現につながります。
【個人の受託者が向くケース】
- 信託期間が短い、相続人が少なく、信託の目的が家族内で完結する
- 信託財産が比較的シンプルで規模が小さい
- 受託者が信託財産やその管理に詳しい
上記のようなケースでは、法人化のよるランニングコストと比較しても、信託財産から生み出される収益が少ないような場合であり、個人受託者の方がコストを抑えることにつながります。
また、信託財産が自宅不動産であるケースでは、信託内容をよく理解している人物が管理をする方が適していると言えます。
信託の目的が認知症対策であり、生活費の管理や介護費用の捻出であるような場合には、家族の事情をよく理解している人物が、受益者のニーズに迅速に対応できると考えられます。
また個人受任であれば、単純に法人のような運営コストが発生しませんので費用を抑えることにもつながります。
家族信託の受託者の法人化については弁護士西田幸広の「この街の相続」へご相談ください
これまで確認してきたように、家族信託の受託者を法人にすることは、安定した長期的な運用が可能になるというメリットがあります。
また、受託法人として設立する法人は中立的な立場で信託財産を管理できる「一般社団法人」が良いでしょう。
弁護士西田幸広の「この街の相続」では、家族信託を一世代のみの信託ではなく、中長期的な資産活用の観点からも安定した承継をできるようにサポートを行なっています。
不動産収益や事業承継を目的としたご相談に関しましては、弁護士西田幸広の「この街の相続」へご相談ください。
相続についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください



